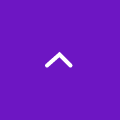メール訓練だけでは足りない?セキュリティ教育の落とし穴とその解決策
組織の情報セキュリティ対策として、メール訓練は今や定番となっています。
特に標的型攻撃メール(いわゆる「なりすましメール」)への対応力を高める目的で、多くの組織が定期的にメール訓練を実施しています。
しかし、こうした「一般的なメール訓練」には、見過ごされがちな欠点がいくつか存在しています。
今回はその課題を整理し、より効果的なセキュリティ教育のあり方について考えてみましょう。
目次[非表示]
一般的なメール訓練の主な欠点とは?
開封率・報告率などの数値が信憑性に欠ける
メール訓練の成果として「開封率」や「報告率」がよく用いられますが、これらの数値は訓練メールの内容や送信タイミング、部署の業務状況などに大きく左右されます。
たとえば、人事部に「履歴書添付」のメールを送れば開封率は高くなりますが、それ以外の部署に関しては開封率が低くなり、メール訓練の効果も薄くなります。
つまり、数値だけでは本当のリスク感度は測れないのです。
開封者だけが教育対象になる偏り
一部のメール訓練では、メールを開封した人だけに注意喚起や教育を行うケースがあります。
これでは、開封しなかった人が教育の機会を得られず、潜在的なリスクが放置されることになります。
実際の攻撃との乖離
訓練メールが「いかにも怪しい」文面で構成されていると、現実の攻撃メールとのギャップが生まれます。
最近では、AIによって自然な日本語で構成された巧妙な攻撃メールも増えており、訓練が現実に即していないと実際の攻撃に対応できない可能性があります。
訓練疲れによる関心の低下
同じような訓練が繰り返されると従業員の関心が薄れ、「またか・・・」という訓練疲れが生じます。
これにより、訓練の効果が低下し、セキュリティ意識の向上につながらなくなります。
業務への支障や不満の発生
訓練メールが業務時間中に送信されることで、業務の混乱や従業員の不満が生じることがあります。
特に繁忙期や重要な業務の最中に訓練が行われると、「忙しい時に何をしているのか」といった声が上がることもあります。
メール訓練を補完するのに最適な「セキュアプラクティス」
こうした欠点を補うには、単なる「開封率の測定」ではなく、実際の行動や判断力を育てる体験型の教育が必要です。
そこで注目されているのが、株式会社ハイパーが提供する「セキュアプラクティス」です。
疑似感染体験による行動変容
セキュアプラクティスでは、マルウェアに感染したかのような疑似体験を通じて、ユーザーが「なぜその操作が危険だったのか」を自ら考える構成になっています。
これにより、単なる知識ではなく「行動の変化」を促します。
実際の攻撃に近いシナリオ設計
ランサムウェアやビジネスメール詐欺など、実際に発生した攻撃メールをベースにしたシナリオが用意されており、リアリティのある訓練が可能です。
誤操作をあえて体験させる設計
誤った操作を行わないとシナリオが進行しない仕組みになっており、ユーザーは「失敗を通じて学ぶ」ことができます。
これにより、危機感や注意力が高まります。
継続的なシナリオ追加と更新
毎年新しいシナリオが追加され、最新の攻撃手法にも対応しています。
訓練疲れを防ぎ、常に新鮮な学びを提供します。
推奨される併用トレーニング
メール訓練と併せて、以下のようなトレーニングを組み合わせることで、より効果的なセキュリティ教育が実現できます。
トレーニング手法 | 補完する欠点 | 内容 |
セキュアプラクティス(体験型) | 開封率偏重、リアリティ不足 | 疑似感染体験、誤操作体験、行動ログ取得 |
インシデント対応トレーニング | 実際の対応力不足 | 初動対応、報告フロー、技術者向け演習 |
定期的なEラーニング | 知識の定着 | 情報セキュリティの基礎、 サイバー攻撃の種類など |
集合研修・ワークショップ | 意識の共有 | 部署横断でのケーススタディ、 ディスカッション形式 |
さいごに
メール訓練はセキュリティ教育の第一歩としては有効ですが、それだけでは不十分です。
実際の攻撃に近い体験を通じて「自分ごと」として捉えることが、真の行動変容につながります。
セキュアプラクティスのような体験型教育を取り入れることで、従業員のセキュリティ意識を根本から高め、組織全体のリスク耐性を強化することが可能になります。
「訓練をやっている」だけで満足せず、「訓練が効いているか」を見直すことが、これからのセキュリティ教育には求められています。